

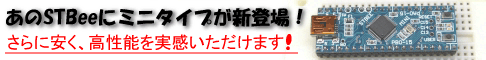
トップページに戻る(マイコン徹底入門:STM32で始めるARM/Cortex-M3組み込み開発)
「マイコン徹底入門」とは? | 「マイコン徹底入門」を読む | ダウンロード | 掲示板 | 筆者の自己紹介


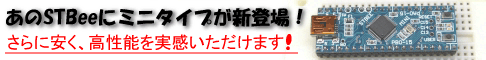
Previous: 3.1.4. 方位センサ |
Up: 3.1.4. 方位センサ |
Next: 3.1.4.2. サンプルプログラム(シリアル出力) |
次はちょっと変わったセンサを利用してみましょう。米Geosensoryが発売しているRDCM-802です(写真 8?21)。秋月電子や共立電子で販売されています。
写真 8?21 RDCM-802をユニバーサル基板に載せた
***P2200733***

RDCM-802は、5Vの電源を供給するだけで、モジュールの向いている方角を、3ビットの出力で表現します。デジタル出力ですから、マイコンのGPIOを利用して簡単に機器の方角を取得することができます。なおメーカーがホームページで配布している説明書のビット表は間違いがありますので、表 8?18を使用してください。
表 8?18 ピン出力と方角の関係
***再トレース***
|
|
N(北) |
NE(北東) |
E(東) |
SE(南東) |
S(南) |
SW(南西) |
W(西) |
NW(北西) |
|
D0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
D1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|
D2 |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
出力ピンはLEDを点灯させられる程度の出力電流があります。マイコンに接続する前に、図 8?56のようなか回路で、ちゃんと動作するか実験してみましょう。
図 8?56 実験用の回路図
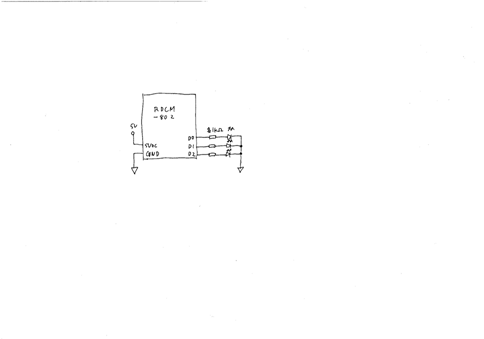
なおこのモジュールは別の基板の表面への実装等を想定しているようで、そのままではブレッドボードに差し込むことができません。両面ユニバーサル基板の表面に半田付けしてしまうという方法もありますが、再利用が難しくなります。そこで筆者は、ヘッダピンを付けたユニバーサル基板にRDCM-802を両面テープで貼り付け、電源、出力ピンからヘッダピンまでをジャンパ線で配線しました。
このあたりは工夫のしどころですので、皆さんも接続しやすい方法を考えてみてください。ちなみに配線を基板の上を通すと電線から発生する磁力により検出結果に影響を与えます。配線を通すとしても基板の回りを大きく迂回させ、センサの付近を通さないようにしましょう。
検出の特性ですが、あまり地磁気が弱いと検出を誤ってしまうようで、屋内では正確な検出結果が得られなかったり、検出結果を誤ったりする場合があります。また筆者の環境では、北向きと判断する角度の範囲(幅)は20°程度だったのに対して、南東向きとする角度の範囲は70°近くあり、各方向での検出の特性が一致していませんでした。地磁気の強さは日々異なりますので、日によっては調子が悪いということもあり得ます。このような特性を踏まえた上でこのセンサーを利用しましょう。
Previous: 3.1.4. 方位センサ |
Up: 3.1.4. 方位センサ |
Next: 3.1.4.2. サンプルプログラム(シリアル出力) |