

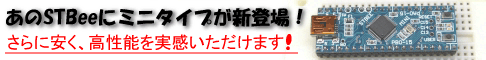
トップページに戻る(マイコン徹底入門:STM32で始めるARM/Cortex-M3組み込み開発)
「マイコン徹底入門」とは? | 「マイコン徹底入門」を読む | ダウンロード | 掲示板 | 筆者の自己紹介


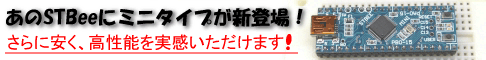
Previous: 3.2.5.3. ドライバIC |
Up: 3.2. FETを利用したHブリッジ |
Next: 4. ADC |
FETを高電流で使用する前に、FETの電流容量と放熱量との関係を理解しておく必要があります。
多くの場合、パワーMOSFETのデータシートは冒頭部分で、そのFETに流せる最大電流量が記載されています。しかし実際には、そのままでは記載された最大電流量を流すことはできません。というのもこの最大電流量は「FETに電流を流したときに発生する熱を完全に放熱し続けることのできる環境においた場合」という前提があるからです。
パワーMOSFETはオン抵抗が非常に少なく、FET内部で発生する損失は、流れている電流量からすればわずかです。もっとも、パワーMOSFETは流す電流量がとても大きく、損失も無視できないだけの量が発生します。例えば2SJ334のオン抵抗は29mΩですが、ここに最大電流である30Aを流したとします。そうするとFETでの電圧降下は870mV(30A×29mΩ)となります。電力量を計算すると、26.1W(870mV×30A)となります。26.1Wというと、筆者が使用している電子部品用の半田ごての消費電力量(20W)を超えています。この電力が熱に変換されているわけですから、放熱しなければFETがすぐに溶けるなり焼け焦げるというのは容易に想像できるでしょう。
そこでパワーMOSFETを使用する場合には、設計時に、想定される電流量を前提としたときに、放熱が必要なのか、放熱が必要なのであればどの程度のサイズの放熱器を取り付ける必要があるのかを見定めておかなければいけません。ちなみにFETだけでなく、パワー(バイポーラ)トランジスタはもちろん、3端子レギュレタ、ソリッドステートリレー、トライアック等も発熱量が大きいですからでも同様の計算を行って、熱設計を行っておく必要があります。
この計算にあたっては熱抵抗(Thermal resistance)という値を用います。熱抵抗は、電気回路での抵抗と同様の概念で、熱の伝わりにくさを数値化したものです。通常、単位は℃/Wを用います。℃/Wは1ワットの熱量の放熱に必要な温度差を表します。
例えば熱抵抗が20℃/Wとなっている発熱体は、1ワットの放熱のために、その周辺の温度が少なくとも20℃低くなければいけないということになります。この発熱体が3ワットの熱を発生するのであれば60℃の温度差が必要です。この場合周辺温度が20度であれば、その発熱体の温度が80℃まで上昇するとこの温度差を満たすということになります。最も80℃まで上昇する前に熱で壊れてしまうような部品であれば、これだけの発熱をさせる利用ができないということになります。そこで発熱量を減らすか、放熱器を付けて熱抵抗を減らすことが必要になります。
パワーMOSFETのデータシートには、熱抵抗の特性が記載されていますので、ここから熱抵抗を計算します。まず放熱器をつけない場合には、「チャネル・外気間熱抵抗」や「Thermal resistance : Junction-to-Ambient」が該当する熱抵抗です。TO-220パッケージのパワーMOSFETであれば62℃/W程度のはずです。放熱器を付ける場合には、パワーMOSFETの「チャネル・ケース間熱抵抗」や「Thermal resistance : Junction-to-Case」に、放熱器の熱抵抗と、FETと放熱器の接合部分の熱抵抗を合計します。TO-220のフルモールドパッケージのケース間抵抗は3℃/W程度、金属がむき出しのパッケージのケース間抵抗は1.5℃/W程度です。TO-220パッケージ用の小型放熱器(20mm×25mm×15mm程度のもの)で20℃/Wから25℃/W程度です。接合部分の熱抵抗は、シリコングリスやシリコンシートを使って密着度を高めた場合には0.5℃/W程度、そのままつなげた場合には2.0℃/W程度です。2SJ334にシリコンシートを使って小型放熱器を付けたときの熱抵抗は28.5℃/W(3+20+0.5)ということになります。
次に部品の最大耐熱温度を確認します。データシートに「絶対定格:チャネル温度」や「Operating Junction Temperature」と記載されている温度です。2SJ334の場合は150℃です。もっとも最大定格は「一瞬でも超えてはいけない値」のため、余裕を与えて信頼性を高める(ディレーティング)ためには、1割から2割は低めに見積もった数値を使用します。実際、基板上の部品が150℃にもなっているとうっかり触れるだけでやけどをしてしまいます。ここでは1割差し引いて135℃としておきます。
最後に周辺温度を決めておきます。普通室内であれば25℃程度ですが、空調が効いていなかったり、屋外で使用したりする場合もあるでしょうから35℃としておきます。なおこれはFETが常に外気に触れられる状況であるということが前提になりますから、FETがケースに入っていて風通しが悪い場合には、かなり高めに見積もっておく必要があります。
前提となる数値がそろいましたので、ここでまずは、放熱器を付けずに流すことのできる電流量を求めてみましょう。使用するFETは2SJ334、電源電圧は7.2Vとします。周辺環境の温度差は100℃(135℃-35℃)です。すると許容される発熱量は100℃÷62℃/W=1.61Wとなります。発熱量(電力量)は電流×電圧であり、電圧は電流×抵抗ですから、電流×(電流×抵抗)なります。各数値を代入すると、電流2×0.029=1.61Wとなり、電流は約7.5Aとなります。この数値を見てわかるとおり、放熱器を付けなければ、最大電流容量の4分の1程度の電流しか流せないということがわかります。
小型放熱器を取り付けた場合の許容発熱量は100℃÷28.5℃/W=3.5Wとなり、電流値は電流2×0.029=3.5Wにより、11Aとなります。若干ですが最大電流量が改善されました。
逆に最大電流量を流せるだけの放熱器の大きさを考えてみましょう。最大電流量を流したときの発生熱量は先述の通り26.1Wです。周辺温度差は100℃という前提ですから、熱抵抗は100℃÷26.1=3.8℃/Wとなります。2mm厚アルミ板の放熱板の熱抵抗の目安は50cm2で10℃/W、100 cm2で7℃/W、200 cm2で4℃/W、500 cm2で3℃/Wぐらいです。そうすると必要な放熱板の大きさは200 cm2強ということになります。200 cm2というと20cm×10cmですから、かなりの大きさですね。
ちなみにFETはFET自体を並列につなげることができます。その場合の全体としての許容電流用は並列にした個数分だけ増えます。状況にもよりますが、20cm×10cmの放熱番よりも、TO-220のFET5個の方がコンパクトに実装できるでしょう。そのため流せる電流量を上げたいのであれば、放熱器を付けるよりも、FETを並列にする方が現実的だと思います。
Previous: 3.2.5.3. ドライバIC |
Up: 3.2. FETを利用したHブリッジ |
Next: 4. ADC |